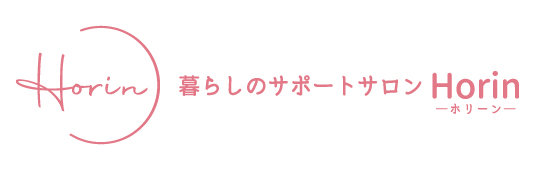【注文住宅】吹き抜けのある家づくりで後悔しないために知っておくべきこと

「吹き抜けって冬は寒い?」
「音が響いて生活しにくい?」
ネットで“吹き抜け 後悔”と検索すると、不安になる声がたくさん出てきますよね。
一方で、
「光が差し込んで開放感が最高」
「家族の気配が感じられる」
といった声もあり、取り入れたい気持ちもあるのではないでしょうか?
吹き抜けは、設計や施工をしっかり考えれば、暮らしを豊かにする大きな武器になります。
この記事では、北近畿・福知山で多くの注文住宅を手がけてきたHORI建築が、吹き抜けのメリット・デメリット、設計で失敗しないためのポイントまで詳しく解説します。
吹き抜けとは?家づくりに取り入れる意味とは
吹き抜けとは、1階から2階(またはそれ以上)にかけて天井を失くした空間のこと。
家の中に開放感と自然光を取り込みやすくするため、多くの注文住宅で採用されています。
限られた敷地でも広く見せることができる設計手法としても人気があり、デザイン性の高さからも注目されています。

吹き抜けのメリット
圧倒的な開放感を演出
吹き抜けをリビングや玄関に設けると、空間に広がりが生まれ、実際の床面積以上に「広さ」を感じさせる効果があります。

光を家の奥まで取り込める
2階部分に窓を設けることで、暗くなりがちな1階部分にも自然光が届くようになり、明るい住空間に。

家族間のつながりを感じやすい
上下階で空間がつながることで、家族の気配を自然に感じることができ、コミュニケーションも生まれやすくなります。

家の中の温度差がやわらぐ(温度のバリアフリー)
空間がつながることで、1階と2階の温度差が緩和され、家の中の温度差が少なくなります。冬の朝、2階から降りてきてもヒヤッとしにくく、夏もムッとした暑さがこもりにくい。“温度のバリアフリー化”により、家のどこにいても心地よく過ごせます。ただし、この効果を最大限に引き出すためには、しっかりとした断熱が不可欠です。

吹き抜けのデメリットとその対策&得られる効果
1. 冷暖房効率が下がるリスク
開放的な空間になる分、断熱材がしっかりしていないと、冷暖房が効きづらくなる可能性があります。
特に冬場は暖かい空気が上に溜まりやすく、1階が寒く感じることも。
対策とその効果:
- 高性能断熱材を採用することで、外気の影響を受けにくくなり室内の温度が安定します。
- シーリングファンで空気を循環させると、上に溜まった暖気を下へ送り、室温のムラを軽減します。
- 床暖房や全館空調と組み合わせると、家全体が均一に暖まり、冬でも快適な住環境を実現できます。

2. 音が響きやすい
家族間のつながりを感じやすい反面、会話や生活音が響きやすく、プライバシーに不安を感じるケースもあります。
対策とその効果:
- 吸音効果のあるクロスやカーテンを取り入れることで、音の反響をやわらげ、落ち着いた空間に。
- 寝室やワークスペースなど静けさが求められる部屋を、吹き抜けから離れた位置に配置することで、生活音の干渉を防げます。
→結果として、吹き抜け空間の開放感を活かしつつ、生活音によるストレスを大幅に軽減できます。

3. 掃除やメンテナンスが大変
高い位置にある窓や照明の掃除・交換がしにくいという声は多く聞かれます。
対策とその効果:
- 手元のスイッチやリモコンで開閉できる高所用窓を採用すれば、無理な作業が不要になります。
- 長寿命LED照明を使うことで、電球の交換頻度をぐっと抑えることができ、維持の手間が格段に減ります。
→結果的に、「手間がかかる」という印象を払拭し、安心して吹き抜け空間を楽しめるようになります。

吹き抜けのおすすめ設置場所アイデア
1. リビング
家族が集まる場所だからこそ、開放感を最大限活かすことができます。

2. 玄関ホール
お客様を迎える場所に吹き抜けを設けることで、第一印象が大きく変わります。

3. 階段・廊下
採光が取りにくい動線部分も、吹き抜けで明るさを確保できます。

4. キッチン上部
調理中でも圧迫感を感じず、ストレスの軽減につながります。

吹き抜け設計で失敗しないためのチェックポイント
1. 吹き抜けの「広さ」は要注意|取りすぎると2階が狭くなる?
吹き抜けを広く取りすぎると、2階の部屋数や収納スペースが減ってしまうことがあります。
たとえば「リビング上を全部吹き抜けにしたら、子ども部屋が1つ足りなくなった…」というケースも。
→アドバイス:
家族構成や将来の生活スタイルを考慮し、2階の必要な居室数を確保したうえで、バランスの良い吹き抜けサイズを設計することが重要です。

2. 吹き抜けに合う断熱・気密性がないと「冬は寒く夏は暑い家」に
空間が広がる分、熱が逃げやすくなるのが吹き抜けの特徴です。
断熱・気密の性能が低いと、冷暖房の効きが悪く、夏は暑く冬は寒い家になってしまうリスクがあります。
→アドバイス:
- 天井や壁の断熱材の種類と厚みを確認
- 窓も高断熱の樹脂サッシや複層ガラスを選択
- スキマ風を防ぐ気密施工も忘れずに
高性能住宅と呼ばれる仕様に近づけることで、快適性と省エネ性を両立できます。

3. 耐震性の確保|大きな空間は「構造の抜け」が生じやすい
吹き抜けにすることで壁が少なくなり、耐震性に影響することがあります。
とくに大地震の際、構造が不十分だと揺れに弱くなる可能性も。
→アドバイス:
- 梁の補強(大梁や化粧梁など)
- 吹き抜けを支える柱・壁の配置設計
- 耐震等級の確認と構造計算の実施
工務店や設計士としっかり相談しながら、見た目だけでなく安心・安全も確保した設計を心がけましょう。

4. インテリアとの相性|「映える空間」にするためのコツ
せっかく開放感のある吹き抜けがあるのに、「照明が暗い」「なんだか殺風景」と感じてしまう方もいます。
設計段階で、吹き抜けの高さに合った照明や装飾を考えておくことが大切です。
→アドバイス:
- ペンダントライトなど高さを活かした照明を選ぶ
- 梁を見せるデザインで木の温もりを演出
- シンボルツリーや大きなアートで縦の空間に視線を誘導
空間を活かしたインテリアで、「住んでいて気分が上がる」おしゃれな家になります。

5. 吹き抜けの位置は「生活動線」と「プライバシー」に直結
どこに吹き抜けを設けるかによって、住まいの快適性が大きく変わります。
たとえば玄関上に吹き抜けを設けると第一印象は華やかですが、寒さが気になることもあります。
→アドバイス:
- リビングに設けると家族のつながりが強調される
- 廊下や階段に設けると家全体が明るくなる
- 寝室やトイレなどプライベート空間は吹き抜けから離す
「吹き抜けをどこに・どのくらい作るか」=家の暮らしやすさを左右する重要な判断です。

まとめ|吹き抜けを成功させるのは「設計力」と「施工力」
吹き抜けは、魅力的でありながら設計や施工に工夫が求められる空間です。
私たちHORI建築では、北近畿・福知山の地域特性や気候も考慮しながら、構造・断熱・インテリアをトータルに設計。
「開放感と暮らしやすさの両立」が叶う理想の住まいをご提案します。
吹き抜けのある家に少しでもご興味がある方は、ぜひお気軽にご相談ください!